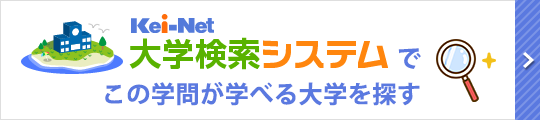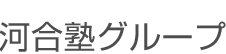史・地理学
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
時間と空間を軸に人間の営みを探究
史・地理学は、特定の時代や地域における人間の営みを探究し、これからの人間社会の在り方やまちづくりを考える学問だ。
史学では、文書や遺跡といった史料に基づき、過去の人間社会や文化などを明らかにする。「日本史」「東洋史」「西洋史」の3つの地域に分かれ、政治・経済・文化などの切り口から研究する。最近では、地域や国家間の関係性に注目し、包括的に歴史をとらえるグローバルヒストリーという試みもある。史料の分析が不可欠なため、対象の時代、国や地域における語学力も要求される。
一方、地理学は地形や産業が人間の営みに与える影響やそこから生まれる地域的特性を考察する学問で、大きく3つの分野に分けられる。「人文地理学」は歴史や文化、政治・経済の視点から地域の特色を研究し、「自然地理学」は地形や気候が人間の生活や産業に与える影響を研究し、「地誌学」は地域ごとの文化や産業などを総合的に研究する。科目には測量学や地図学、地理情報システムなど理系の要素が強いものも多く、フィールドワーク(実地調査)も行う。
大学選びココがポイント
史・地理学は、文学部などの文系学部で学べる。自然地理学は理系学部で開講されていることも多い。大学や教授によって研究分野が異なるので、大学案内などで確認しておこう。
先輩たちの時間割
京都大学 文学部 人文学科 3年 M.N.特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | - | 博物館教育論 | 日本史学(演習Ⅰ) | - | - | - |
| 2限 | - | 東洋史学(講義) | 東洋史学(特殊講義) | 日本史学(特殊講義) | 考古学(特殊講義) | - |
| 3限 | - | 博物館情報論・メディア論 | 日本史学(実習) | 博物館実習(文化史) | - | |
| 4限 | - | 日本史学(特殊講義) | - | - | ||
| 5限 | - | - | - | 東洋史学(特殊講義) | - | - |
| 6限 | - | - | - | - | - | - |
※3年次前期の時間割
おもしろい講義 「博物館実習(文化史)」
大学の博物館で文献史・考古学・地理・美術それぞれの実務を積むだけではなく、様々な博物館の見学に赴くことで様々な展示法を学べます。また許可を得て各博物館のバックヤード・収蔵庫にも入ることができます。
こんな研究しています
大阪大学 文学部 人文学科 卒業 R.M.特派員
兵庫県宍粟市の通所介護施設における機能訓練の地域格差
通所介護施設における機能訓練を県レベルで分析すると、大都市圏外と大都市圏内との間に大きな実施格差が見られる。大都市圏外の小規模市町村である兵庫県宍粟市を対象に機能訓練の実施状況を調査すると、施設内の人員配置に訓練の充実度は大きく左右される。その中で、自治体などを中心として柔軟な雇用形態を実現することが機能訓練の充実につながると考えられる。
実地調査に基づく研究なので、普段関わらない業種の人々と話したり、普段訪れることのない施設を見れたりするのが魅力です。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から史・地理学に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。