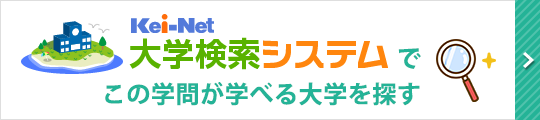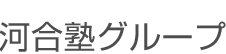農学(生物生産系)
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
食料生産にかかわる研究を行う
農学(生物生産系)は、私たちの食料となる植物や動物を生産する技術を学ぶ分野だ。植物に関する研究が多く、作物の遺伝的な品種改良を行う育種学、農作物の品質や生産性を向上させる作物学、植物の病気を扱う植物病理学、土の性質を学ぶ土壌学などがある。虫の生態・生理を調査し防除に役立てる昆虫学・害虫学を学ぶこともできる。
牛やニワトリといった家畜動物の生態や生産について研究するのは酪農・畜産学だ。飼料の開発や繁殖・育成方法による品質向上のほか、家畜の病気の予防・治療、飼育環境の衛生管理や整備、流通まで幅広く学べる。
このほか、魚など水中の生物の生態を研究し、水産物の養殖や加工・品質管理など水産業全般について学ぶ水産学がある。地球規模での海洋調査も行われており、海洋生物資源の保護や将来の動向を予測する研究も進んでいる。
大学選びココがポイント
生物生産系は、農学系学部の農、園芸、生物生産、生物資源といった学科で学べる。名前だけでは特徴がつかみにくい学科もあるので、大学案内などで研究内容を確認しておこう。酪農・畜産学、水産学は、学べる大学がそれほど多くないので注意が必要だ。
先輩たちの時間割
静岡大学 農学部 生物資源科学 2年 マーナレード特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 有機化学 | 土壌微生物学 | - | - | 園芸学 | - |
| 2限 | 分子生物学 | 心理学 | 植物病理学 | 上級英語 | 植物生理学 | - |
| 3限 | - | - | バイオサイエンス実習 | - | 地域創造特論 | - |
| 4限 | - | 作物学 | - | - | - | |
| 5限 | - | - | - | - | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - |
※2年次前期の時間割
おもしろい講義 「農業環境演習」
通年の講義で、梅が島大代地区にいき、茶の収穫や農作業を手伝いながら、中山間地域の課題について考える。1年から3年まで取る必要があり、現在、日本茶の販売を行っている。また、カフェやテラスを開く計画を立てている。
こんな研究しています
名古屋大学 農学部 卒業 Y.H.特派員
カリウム施与が乾燥ストレス下におけるC3、C4作物の光合成および水利用に及ぼす影響の解明
C3作物であるオオムギやコムギ、C4作物であるトウモロコシやシコクビエを、異なるカリウム条件や土壌水分条件で栽培し、ガス交換やクロロフィル蛍光、水消費量などを測定することにより、カリウム施与が乾燥ストレス下における作物の光合成や水利用にどのように影響するか解明することを目的とする。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から農学(生物生産系)に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。