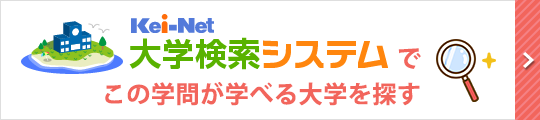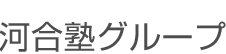教育学・教員養成系
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
教育の本質を学ぶ教育学と教師をめざす教員養成系
教育系は、教育学と教員養成系の大きく2つに分けられる。
教育学は、「教育」を学問として研究する。教員養成を直接の目的とせず、教育の本質や目的、人間形成とのかかわりについて追究していく。哲学や心理学、歴史学、法学、経営学などともかかわりの深い総合科学といえる。
教員養成系学部の「教員養成課程」は、教員免許の取得が卒業要件となっている。1・2年次に教養科目や教育の基礎を学び、3年次以降に子どもの発達過程や免許を取得する教科の指導法など、教師に必要な知識や技術を修得する。教育実習は3年次以降に行われることが多いが、最近は教育実習関連科目として1年次から実習や支援を行う大学も増えている。
一方、教員養成系学部の中には、教員免許の取得を義務づけず、幅広い教養をもつ人材の育成を目的とする「総合科学課程」もある。学校教育に限らず、生涯教育や人間科学、国際、芸術、スポーツなど幅広い分野の教育を総合的に研究する。情報、環境分野と融合したテーマもあり、学際的な研究が行われている。
大学選びココがポイント
教育学は文学部や教育学部で学ぶことができ、専攻・コースとして設置されている大学もある。教員免許を取得したい場合は、教職のための単位を別途取得すれば中学・高校の教員免許を取ることができる。
教員養成系の教育学部は国立大に多く設置されているが、近年は私立大でも増えている。教員採用数は県や市など各自治体によって異なるので、自分が働きたい地域の採用数や志望大学の採用実績にも目を配っておこう。
先輩たちの時間割
大阪公立大学 文学部 4年 かんぱち特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | - | - | - | 日本史通論Ⅱ | 労働と人権 | - |
| 2限 | 人間行動学データ解析法Ⅰ | 教育学演習Ⅲ | - | 教育方法学Ⅰ | 発達・学習論 | - |
| 3限 | 社会学概論Ⅰ | 考古学概論 | - | 社会科・公民科教育法Ⅰ | 教育学概論Ⅰ | - |
| 4限 | 教育学概論Ⅱ | 教育学研究法Ⅰ | - | Sophomore English Ⅰ | 健康へのアプローチ | - |
| 5限 | 教育相談論 | - | 現代の医療 | - | - | - |
| 6限 | - | - | - | - | - | - |
※2年次前期の時間割
おもしろい講義 「教育学演習Ⅲ」
毎回、特色ある教育実践を行った人物についての内容を読み、その特色・評価できる点・課題などを議論します。最後には、教育の歴史の流れや現代につながる点、各教育実践からの学びを整理し、まとめました。人は自分が受けてきた教育しか知らないため、どうしても自分の被教育体験を自明かのように、それを軸に考えてしまいがちです。しかし、この授業で、さまざまな教育実践を知り、他の受講者との議論を交わす中で、教育について多角的・多面的に見ることができるようになったと感じました。
こんな研究しています
お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 修了 みっちゃん特派員
発達障害のある子どもの学校適応について
発達障害の特性をもつ子どもの学校適応を支える要因について、中学生を対象としたアンケート調査による実証研究を行った。統計分析により、発達障害の子どもの学校適応において、自尊感情の育成が重要であることが明らかとなった。
実際にアンケート調査を行って「データを取得する」ことにより、客観的に結果を示すことができる点が面白い。統計分析によって、実証的に人のこころについて明らかにできる点が魅力である。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から教育学・教員養成系に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。