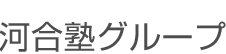住居学
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
豊かな住生活の実現をめざして
住む人の立場から見た快適な住空間を考え、実現していくのが住居学だ。子どもから高齢者までが安全で健康的に暮らせる、機能的な空間を創造していく。たとえば、バリアフリー住宅や狭い敷地でもくつろげる空間づくりなどがその対象だ。また、住居を取り巻く地域の文化や人間関係、都市の環境なども研究対象となる。
大学ではまず住居学の基礎とともに設計や製図の方法を学び、その後コースや専攻に分かれて設計製図や材料実験、実測調査など専門性の高い実習・演習に取り組む。インテリアのデザイナーやコーディネーターをめざすならこの学問を学んでおこう。
大学選びココがポイント
住居学は家政学部、生活科学部などに設置されている生活環境学科や環境デザイン学科、居住環境学科などで学ぶことができる。一級建築士、二級建築士、木造建築士の受験資格を得られる大学もある。自分の学びたい分野が設置されているか、大学案内などで確認しておこう。
先輩たちの時間割
奈良女子大学 生活環境学部 住環境学科 3年 N.O.特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 地域居住学 | - | 建築装備学 | - | - | CAD演習 |
| 2限 | - | 英語 | - | - | 英語 | |
| 3限 | 建築環境学 | 建築構造計画学 | - | 住居管理学実習 | 緑地環境計画論 | |
| 4限 | 住環境デザイン基礎 | - | 設計演習 | |||
| 5限 | - | 固体地球環境学 | 空間デザイン学 | - | ||
| 6限 | - | - | - | - | - |
※2年次後期の時間割
おもしろい講義 「緑地環境計画論」
ランドスケープと建築を同時に学べる大学は数少ないと思います。担当講師の方の実務経験の話やランドスケープが素晴らしい建築物を知ることができ、興味の幅が広がりました。
似たもの比較~建築学と住居学~
住居学科でも建築学科と同じように設計や構造力学など建築学の基礎を学べる大学が多い。建築学も住居学も建物を扱う点は同じだが、いったいどこが違うのだろうか?
建築学が建物の構造や強度、建築材料などのハード面を重視するのに対し、住居学では健康的で豊かな生活を送る住環境の実現といったソフト面から建物を考える。そのため、住居学ではインテリアなどの内装も研究対象となっている。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から住居学に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。