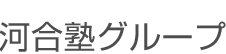経済学
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
絶えず変化する経済現象を分析
経済学というと、難しく感じる人もいるだろうが、実は私たちの生活にかかわる身近な学問だ。景気変動や物価の上昇など経済現象のメカニズムを分析し、その理論を実社会に役立てていくことが、経済学には求められる。
経済学では主に理論と応用方法を学ぶ。理論には、個人や個々の企業の経済活動を考えるミクロ経済学、日本やEUといった国や地域圏の景気動向などを分析するマクロ経済学がある。応用には、実社会の制度設計にも深くかかわっていく財政学、金融学、公共経済学や国家間の貿易を扱う国際経済学などがある。
経済学には実際のデータに基づいた検証が欠かせないため、さまざまな統計データを分析する手法も身につける必要がある。コンピュータを用いてシミュレーションを行い、経済動向を予測するため演習を設けている大学も多い。
先輩たちの時間割
京都大学 経済学部 経済経営学科 2年 K.F.特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 財政学 | - | - | - | 会計学 | - |
| 2限 | 都市経済学 | - | - | 女性キャリア論 | ドイツ語 | - |
| 3限 | マクロ経済学 | 統計学 | urban planning | 人文地理学 | - | |
| 4限 | 外国文献研究 | 労働経済学 | ミクロ経済学 | 投資銀行業務 | - | - |
| 5限 | - | - | - | - | - | - |
| 6限 | - | - | - | - | - | - |
※2年次前期の時間割
こんな研究しています
学習院大学 経済学部 経済学科 卒業 白の冒険家特派員
英国鉄道史と日英鉄道の比較
世界経済史の中では外すことの出来ない産業革命と、そこで発展した鉄道を組み合わせた論文を執筆しました。蒸気機関の起源から始まり、産業革命のなかで鉄道がどのような役割を持っていたのか、どのような影響をもたらしたのかについて触れ、日本の鉄道についても触れました。
「鉄道」と聞くと経済と関係ないと感じる方もいるかもしれません。しかし上記の通り、世界経済を動かした英国の産業革命の下で鉄道は生まれました。日本の鉄道も、特に東海道新幹線は高度経済成長の下で生まれるなど、世界的に見ても鉄道は経済と密接な関係を持っていると言えます。大学は一見関係なさそうなものでも、それを学問としてどのように捉え、どのように研究するかを考え得る場所です。
似たもの比較:経済学と経営学
同じ「経済活動」という現象を扱う学問だが、経済学は社会全体の経済活動に問題意識をもって理論分析をするのに対し、経営学は組織のマネジメントや行動原理を研究する。単に分析するのではなく、いかに行動すべきかを問題とし、実践に応用するのが経営学の視点だ。
理系の学問に例えると、経済学は自然界の法則性を探究する物理学に、経営学はその法則を踏まえながら、いかに人間に役立てるかという工学に似ている。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から経済学に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。