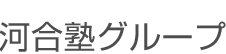航空・宇宙工学
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点のものです。
何を学ぶの?
最先端技術を結集した総合工学
航空・宇宙工学は、航空機やロケット、人工衛星や宇宙ステーションなどを研究・開発する学問だ。その設計・製造・運用の理論を学ぶため、物理学や機械工学、材料工学、通信・情報工学などを結集した総合工学といえる。
学ぶ分野は、空気抵抗や浮力を研究する流体力学、機体の構造・設計に関する構造力学、飛行に必要なエンジンを研究する推進工学、機体の操縦性能や飛行の安定性を追求する航空・制御工学の大きく4つに分かれる。これらの分野を軸に、学ぶ内容は広範囲にわたる。進歩が著しい分野で、最先端の技術にも触れることができる。
大学ではまず基本となる数学や物理を勉強し、高年次になると宇宙や航空に直接関連した科目を学ぶ。華やかに見えるこの分野だが、実は地道な研究の連続。コツコツと努力を積み重ねることが必要な分野なのだ。
大学選びココがポイント
航空・宇宙工学系学科をもつ大学は数が少ない。物理や化学などの高度な知識だけでなく、語学力も求められる。「航空」「宇宙」という名称が含まれない機械系や通信・情報系、材料系学科でも航空機や宇宙を対象として研究している大学もあるため、どの大学でどのような研究に取り組めるかをしっかりと確認しておこう。
先輩たちの時間割
名古屋大学 工学部 機械・航空宇宙工学科 4年 T.K.特派員の時間割
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | ディジタル回路 | 振動工学第2及び演習 | - | 加工学第1及び演習 | 制御工学第2及び演習 | - |
| 2限 | 材料科学第2 | - | - | |||
| 3限 | アクチュエータ工学 | 電子回路 | 機械・航空宇宙工学実験第1 | - | - | - |
| 4限 | 数値解析法 | 計測基礎論 | - | 設計製図第2 | - | |
| 5限 | - | 工作機械工学 | - | 宇宙推進工学 | - | |
| 6限 | - | - | - | - | - | - |
※3年次前期の時間割
おもしろい講義 「設計製図第2」
アームロボットを設計コンセプトや使用する部品をコストなども考慮して自分で決め、製図まで行う。2年次までに学習したことが全て活きてくる総合的な学習で面白いと感じた。
こんな研究しています
九州大学大学院 修士課程 H.M.特派員
航空エンジン燃焼器内における燃料モデルによる燃焼の違い
実際の航空燃料であるケロシンは、自動車に使うガソリンと同様に複数の化学種から構成される。そのため、CFDでシュミレーションする際には航空燃料の規格に近い代替化学種を用いて燃焼解析を行う。私が行った実験では2つの化学種モデルを用いて数値計算を行い、発生する有害物質が実際の値とどのくらい違うのかという研究を行った。
もっと学問を掘り下げる
Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」では、学問をさらに細かく分類し、その学問を学べる大学や活躍する研究者、関連する書籍などをご紹介しています。ここでは、その中から航空・宇宙工学に関連する学問の一部をご紹介します。
※Kei-Netの協力サイト「みらいぶっく」へリンクします。